こんにちは、darakeです。
今回の記事では、コロナショックによって学校と教師の「変化」について考えます。
長い学校の歴史の中で『当たり前!』と思われていたものが、このコロナショックの影響で揺らぎ始めています。奇しくもそれに気づかせてくれたのが、最悪のウイルスコロナちゃんです。
具体的な内容は次の2点です。
- 学校はソーシャル・ディスタンシングとの相性最悪
- ティーチングとプランニングの使い分け
学校はソーシャル・ディスタンシングとの相性最悪
ソーシャル・ディスタンシングとは社会的距離という意味で、人込みを避けて人との距離を確保することを指します。
コロナウイルスの感染拡大を受けて、注目されている言葉です。
この社会的距離は、人と人が手を伸ばして届く距離ということなので、約2mぐらいでしょうか。
この言葉を聞いてすぐに頭に浮かんだのは、
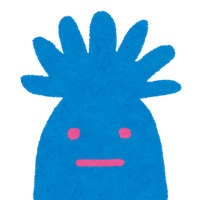
学校にソーシャル・ディスタンシングは存在しないな!
1クラス20人以上が集まる学校では、左右前後で2m離すことなんて不可能です。ソーシャル・ディスタンシングを実践できる学校は小規模校ぐらいしかありません。
考えてみると、学校という環境は感染症とすこぶる相性がよくありません。インフルエンザが流行する季節になると、必ずどこかの学校が閉鎖になっていますよね。
左右前後1mも離れていない空間で6~7時間を共に過ごすため(途中食事も一緒にして)、決して衛生的とはいえない環境です。この狭い空間の中、向かい合ってお喋りしながら食事をします。
しかも、水分補給は共有の水飲み場を多くの生徒が使用します。使った蛇口を上のままにしておく生徒もいて超不衛生です。
さらに、男子中学生はハンカチ持ってないやつが多いので、適当な手洗いをして服で拭きます。
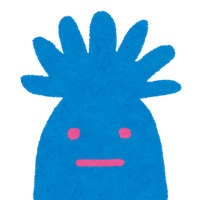
学校は、Notソーシャル・ディスタンシングやね!
コロナウイルス感染の拡大を防ごうとしたら学校閉鎖は絶対であり、誰もが疑わないでしょう。対感染症という観点からすると、学校ほど危険な場所はないですね。
外出を控えるように言っておきながら、生徒たちに外出させて感染リスクの高い場所へと集めます。そして、密集と密着を継続しながら飛沫感染経路を確保しています。
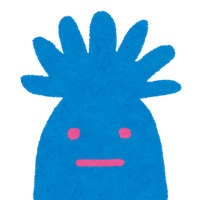
生徒たちと同様に、教師も常に感染リスクにさらされているのね・・・
ティーチングとプランニングの使い分け
学校で教師が学習を教える。
これが学校の存在意義で、当たり前のことと認識している人が多いでしょう。
戦後、多くの日本人が学校で教師に学習を教わってきたので、それを疑うことすらしていないのです。今だに学習は学校でする・教師に教わるという固定観念から抜け出せない人がたくさんいます。
教師たちも例外ではなく、それを否定すると教師の存在意義が揺らいでしまうと考えてしまう人たちが多いのです。
けれども時代は変わり、塾や家庭教師といった選択肢が増え、クオリティの高い専門動画が増えたことで、学校だけが学習を教える場ではなくなりました。
もっと言うと、教科書の内容だけを学習していていれば幸せな人生が待っていた時代は終わっています。
このことはコロナウイルスが流行する前から明らかになってはいましたが、コロナウイルスによって決定的となり、システム変更を余儀なくされています。
なぜなら、1か月臨時休校になったことで学校の存在意義が失われました。学校で生徒に学習を教えることが強制的にできなくなりました。
教師の中心業務でかつ専門分野である、「教える」ということができなくなったわけですね。
つまり何が言いたいかというと、今までの「教える」という役割にプラスして、「学習企画者」という役割が必要になったのです。
各生徒に対して、何を学習すればいいのか,どんな教材を使い、どのように進めたらいいのかを企画して導くことが必要になっています。
教える者がいなくても、生徒たちが自分で学習を進めていけるようにプランニングできる教師が必要です。
コロナウイルスによって休校延長している学校が多く、動画授業を準備している教師も多いでしょう。
ただ、動画撮影素人の教師が今から動画を撮るよりも,すでにあるわかりやすい動画を活用した方が効率が良さそうです(興味がある人のことは否定しません)。
darakeが今やっていることは、
・各家庭のネット環境の把握(持っている機器、通信契約等)
・家で1人でも学習が進められるシステムを示す
・問題集の使い方と進めるスピードの目安を具体的に示す
・ZOOMなどのアプリを実用すること
・オンライン上では学習企画の修正・再提示に重点
・ネット上に山ほどある専門性の高い動画を推奨する
・どの動画をどのタイミングで見ればよいかの提案
現状、学校でティーチングしていた内容全てを、オンライン上で網羅することは難しいでしょう。
ならば、生徒が各自で学習を進めていけるシステムを作り、オンライン上では生徒の疑問や悩みを解決することに重点を置いた方が良さそうです。
幸いなことに、文部科学省からこんな特定通知が出ました。
休校中の児童生徒が家庭学習を通じて学力を身につけたと確認できる場合、学校再開後に同じ内容を授業などで扱わなくてもよいとする特例の通知を出した。
ただ、『休校中に評価しなさい!』は横暴だからやめたらいいです。
今後コロナショックが落ち着いたとしても、必ずまた何か(災害、別の感染症)の危機には直面します。だからこそ、ティーチングとプランニングができる教師になっておいた方が良さそうです。
おわりに
今回は、コロナショックによって学校と教師が「変わるべきこと」について考えました。
・ソーシャル・ディスタンシングなんて相性最悪!
・学校だけが学習する場という考えは古い
・ティーチングだけの教師は時代に埋もれる
・ティーチングとプランニング両方できる教師に!
コロナショック下では、多くの教師が国・数・社・理・英の5教科を優先しようという風潮が強いですが、果たしてそれが納得解でしょうか?
生徒の気持ちになって考えた時、音楽・技家・美術・保体の実技4教科の方が求めていそうな気がします。狭い教室で感染リスクを高めるより、広い場所で実技4教科を学んだ方が・・・。
と思っている生徒もいるかもしれませんね。
とにかく、コロナショックで文句や嘆いているだけでは前に進めないので、何ができる教師が意味ある存在なのかを自問自答していきましょう。
今回はここまで!
みなさんが、幸せな人生を送れますように!





コメント