こんにちは、darakeです。
今回の記事は、以前の記事の続きとなります。ZOOMを使ってオンラインで生徒と教師を繋いでみた検証結果をまとめています。
まずはコチラ↓から読んでもらえると嬉しいです。
具体的な内容は次の2点です。
- オンライン一斉授業はハードルが高い
- オンラインは使い方によっては有効な手立て
オンライン一斉授業はハードルが高い
中学生のスマホ・タブレット所持率は100%ではありません。
まず、今の公教育を取り巻く環境でのオンライン一斉授業は難しいです。学校の機器を貸し出したり、Wi-Fiルーターを貸し出して通信費用を援助するにしても、100%の環境を整えるには至らないでしょう。
これがすぐに出来るのならば、なぜ今までやらなかったの?って話ですから。スピードが求められている中で現実的な話ではありません。
と言いながらも、本校では早くからZOOMを使ってオンライン相談会を実施しています。ネット環境が整っていない家庭については電話対応で勘弁してもらっています。
緊急時に公平性を気にしていたら何も始められないので、まず実行に移しました!※2020.4.23、文科省が平常時のICT活用ルールに捉われなくていいという通知を出しました!その通りで、遅いぐらいです!
ただ、仮に今後ネット環境が整ってオンライン授業が可能になっても、中学生には一斉授業形式は効果が薄いということです!
以下の3点を課題として挙げます。
2複数参加になると当然講義形式になる
3疑問や発言がなければ双方向の意味が薄れる
一斉に参加させるためのハードルが高い
中学生が一斉にオンライン授業に参加するためには、関心・意欲の高さ、強制力、メリットが必要になります。
そもそも、その授業に関心・意欲がないのであれば参加してこないでしょう。
どうしても参加させたいのであれば、そこに強制力を足さないといけません(単位や出席扱い等)。
高校生や大学生には単位取得のためという強制力が働きますが、中学生にはそれはない。強いて出来ることは、オンラインに参加しないと欠席とする(すぐクレーム入るでしょう)。
または、『あの先生の説明を聞きたい』というメリットがあるかどうかです。
これら3つのどれかがないと、中学生を一斉にオンライン授業に参加させるのは難しいでしょう。
複数参加になると当然講義形式になる
オンライン相談会を実施してわかったことは、10人以上が一斉にZOOMに参加してくると全員の相談を受けきれません。
1人の質問に対応してしまうと、残り多数が放置になります。そうすると、『俺もそれ聞きたかった』グループと『それ既にわかってるし』グループができてしまう。
また、生徒が個々に発言してしまうと収拾がつかないので、教師はそこを指摘しながら説明や話を聞くことを徹底させなければいけません。
なので、中学生向けに一斉オンライン授業をやろうとすると、静かに教師の話を聞く講義形式にならざるを得ないのです。
ここで疑問が1つ。
オンラインで繋いで教師の説明を聞くだけならば、わかりやすいyoutube動画を見る方が良いという生徒が出てくるでしょう。なぜなら、好きな時に見る・やめるが可能だし、質も高いため。
疑問や発言がなければ双方向の意味が薄れる
では、講義形式にしないでオンライン授業を実施する場合について考えてみます。
この場合、疑問を質問したり何らかの生徒からの発言がなければオンラインで繋ぐ意味がなくなります。にも関わらず、相談会を実施していて気付いたのは、オンラインで繋いでも発言する生徒が少ないことです。
そもそも、ZOOMをビデオオフにしたり自分の音声をオフにする生徒もいました。これはただ興味本位の参加か、教師の話を聞くだけという意思表示です。
その他には心理的な要因も関係していると思います。
多くの生徒が参加しているオンライン上では発言しづらいという理由です。実際、積極的に質問していたのは日頃から物怖じしない生徒たちでした。
オンラインは使い方によっては有効な手立て
では、オンラインで繋ぐ意味はないのでしょうか?
断言できますが、これは否です! オンラインは使い方次第で有効な手立てとなります!
中学校のオンライン授業は、少数グループで構成するとその威力を発揮します。5人以下だと質問もしやすく、生徒のニーズにも柔軟に答えることが可能です。
生徒たちも参加人数が少なくなるにつれて、質問や発言しやすくなるようでした(慣れにもよると思います)。
生徒の中には家庭教師のような使い方をして、マンツーマンでの個別指導を受けている子もいました。これは有効活用をした良い例です。
これらを踏まえての改善点としては、オンラインで繋ぐ目的を明確にすることが大切でしょう。
例えば、コミュニケーションをとることを目的にするなら人数制限は必要ありません。ZOOMに参加してきた全員でワイワイ会話するだけでも効果はあります。
また、全員に一律で伝えたい内容であれば人数制限する必要がなく、短時間で繋げば事は足ります。そして、その後に個別グループを編成して、質疑応答を受けるのもいいでしょう。
ZOOMでは参加者の管理ができるので、人数が多くなりそうであれば参加許可しないことも可能です。参加できなかった生徒は、次の時間に回ればいいだけです。
結論として、オンライン授業が今までのオフラインでの授業に成り代わることはまだ無理です。
ただ、疑問解決のための質問窓口としては、とても有効な手立てとなります(放課後開設して受験対策など)。
おわりに
今回は、ZOOMを使ってオンラインで生徒と教師を繋いでみた検証結果をまとめました。
・中学生がオンライン授業に一斉参加することはハードルが高く、教育効果も薄い
・参加する側が質問や発言をしない限り双方向で繋ぐ意味が薄れる
・目的に応じて参加人数を分けると効果が上がる
・個別に疑問解決する手立てとしては有効である
・うだうだ言ってないでやってみると良い!笑
ZOOMのような双方向での繋がりは、参加するための意欲や興味・関心が高い人たちの集まりでないと、ただのパフォーマンスで終わってしまう気がします。
そもそも、自立して学習する習慣が身についていない生徒は、疑問や質問することも見つけられていないため、オンライン授業のメリットが生かせません。
この検証結果をもとに、効果的な使い方を再検討していきます。休校解除になった後も上手に活用できるといいですよね。
オンラインで生徒と繋いだ実験結果から、オフライン授業(従来通りの授業)のアップデートすべき姿が見えてきました(この話はまた今度)。
オンラインの世界は強豪揃いです。クオリティの低い自作授業動画は見てすらもらえません。すぐにおもしろいyoutube動画に切り替えられるでしょう。
なので、今は授業動画を配信する必要はないかなと思いました(時間に余裕がある人はどうぞ)。
今後は、オフライン授業の質を高めつつ、オンラインで補足できるようにするといいかもしれません。オンとオフの共存が大切でしょう。
今回はここまで!
みなさんが、幸せな人生を送れますように!

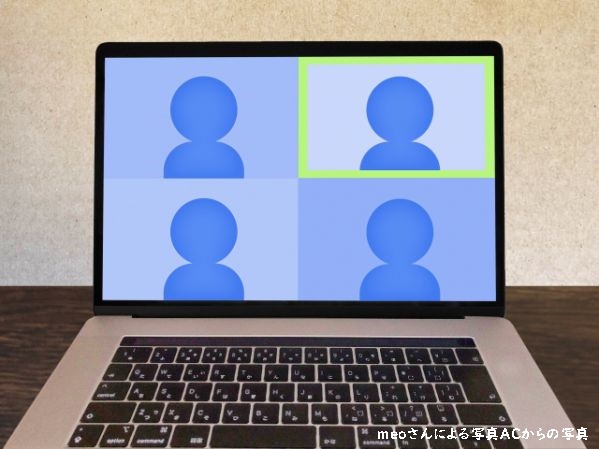



コメント