こんにちは、darakeです。
今回は、お金の使い方を教える実践の場として修学旅行を活用しようという記事です。
なぜこの記事を書こうと思ったかというと、修学旅行における生徒のお金の使い方があまりにも雑だからです。
その様子を見て思いました。
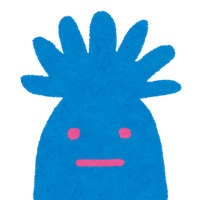
幼少から今までお金の使い方を教わっていないね!
教育に携わる者として、これは放っておくことはできません。まず最初にお金の使い方を教えるのは家庭の役割です。そして、身近にいる大人です。
教えるためには、自らがお金の使い方を理解していなければなりません。以前にも次のような記事をアップしています。まだ読んでいない方は目を通してくれるとうれしいです。
学校教育において、生徒が自らの意思で、一番大きな額のお金を使う場面が修学旅行です。ならば、この機会にお金の使い方を実践させて振り返らせる学びの場を設けましょう。
具体的な内容は次の2点です。
- 修学旅行における学びの流れ
- 何にお金を払い、誰のために使っているのか
修学旅行における学びの流れ
学びの大きな流れとしては、事前指導⇒実践⇒振り返り⇒実生活へフィードバックとなります。
目的としては、修学旅行を通して今後のお金の使い方をアップデートさせることです。
まず、お金が発明された過程を知ること。共同幻想の上に今の経済は成り立っていることを理解することからスタートです。
そして、お金の使い方には大きく分類して3種類(消費・浪費・投資)あることを知る。
これら2つのことを事前に知ってから修学旅行に行くべきです。


事前に学んだお金の使い方を意識しながら修学旅行で実践します。
旅行中に何かを買う時、消費・浪費・投資の分類を頭に思い浮かべることがポイントです。
そして、就寝前に何にどれだけお金を使ったのかをメモします。その際、予め消費・浪費・投資の欄を区別してメモすると後から整理しやすいですね。
旅行から戻ってきた後の活動になります。
旅行中にメモしたお金の使い方に対して、自分自身で振り返ります。振り返る内容は、消費・浪費・投資にどれぐらいの配分でお金を使ったのか。
修学旅行中の「消費」なんてほぼありません。食事に使う分だけです。お菓子や飲み物代は全て「浪費」です。ここに気付けるかどうかがポイントです。
旅行中の「投資」は、将来の自分の財産になり得るかどうかです。今後も得難い体験、現地に訪れることでしか手に入らない情報等です。これを意識してお金を使った生徒がいたら最高です。
修学旅行でのお金の使い方の失敗や成功を通して、日々の生活に活かすことが求められます。何も知らずに「浪費」ばかりを繰り返す人に豊かな人生を送ることはできません。
お金を使い、日々実験を繰り返す生活を推奨します。親の元で暮らし、生活費の心配がいらないからこそ、大胆に実験をすることができます。
何にお金を払い、誰のために使っているのか
旅行中のお金の使い方から、別の学びもできます。
それは、私たちは何にお金を多く払っているのかという気づきと、お土産という存在についてです。
生徒たちの使い方の内訳を見ると、割合の多くを占めるのがお菓子・飲み物・アイスを買う「浪費」です。そして、次を占めるのがお土産です。
「浪費」については日常の生活からコントロールすることが大切です。自分の欲求をコントロールするということです。
結果的に無駄になっているモノ・サービスにお金を使い続けるというのは、お金を捨てていることと同じです。
お小遣いの範囲で使っているうちはダメージは少ないですが、一人暮らしで生計を立て始めてから「浪費」をコントロールできないようなら破滅します。
日本はモノに溢れている国なので、どうしても「浪費」が多くなりがちです。「浪費」だとわかった上でお金を使い、自分の欲を上手にコントロールできる人に育てたいものです。
次に、お土産についての学びです。
お土産は大きく分けて、「自分のため」と「誰かのため」の2つに分類できます。
自分のために買う場合、ほとんど後で要らないモノを買っています。現地の人形、Tシャツ、キーホルダー、テナント、木刀(なぜか買うヤツがいる)など。
ただ、これは「旅行先」という一要素が加わり、財布の紐が緩くなった状態で起こる行動原理なのです。
現地の人が絶対買わないようなモノやサービスを、旅行者たちが購入していく理由にはお土産理論があるのです。自分用のお土産とは、旅行の記憶を思い出すためのツールの役割を果たします。
お土産屋さんが成り立っているには理由があり、それを生徒たちに気付かせるための教材として修学旅行は役立ちます。
また、誰かのためにお土産を買う場合について、お土産という贈り物をする時のマナーを学ぶことができます。
旅行中のノリで買う場合、次の2点がポイントになります。
・相手がもらって困るモノが想像できているか。
『とにかく買って、後は渡して満足!』という問題ではないのです。誰かに渡すのであれば自己満足ではいけません。1つの例を紹介します。
1人暮らしのおじいちゃんに対して、大量のお菓子をお土産として買った場合です。
もしかしたら、食べきれずにゴミになるかもしれない。買った人には悪気はありませんが、処理するのはおじいちゃんです。
もらったモノをゴミにしてしまうのは、気持ちの良いことではありません。
相手がどんなモノを求めているのか、何を喜ぶかを想像してお土産を選ぶことが大切です。とても当たり前のことですが、教わらないで育っている人が多くいるのです(darakeもその一人でした)。
おわりに
修学旅行をお金を使う実践の場とするならば、今までよりも有意義な行事になると思います。
友人との思い出を作るだけで終わらずに、お金の使い方(「浪費」のコントロール)を学び、お土産理論を学び、お土産という贈り物をする時のマナーを学ぶ。
どれも日常の学校教育では学ぶことができないことです。家庭教育でこれらが完了していれば言うことないですけど。#素敵な家庭
お金の話は大人が聞くと『そりゃあ当たり前でしょ』と思うことばかりです。ただ、その当たり前を知らずに社会に出ている若者がいて、彼らに『自分で身につけろ』と突き放す教育は無責任だと思っています。
伝えることで学びキッカケとなるのであれば、1人でも多くに伝えることには価値があるはずです。
darakeは家族と教え子たち、このブログの読者に伝え続けます!
今回はここまで!
みなさんが豊かな人生を送れますように!




コメント